投稿日:2025.3.24
歯並びと老化にはどんな関係があるの?
みなさん、こんにちは。
池袋キュア矯正歯科です。
年齢を重ねると共に「歯並びが悪くなった」「歯の隙間が空いてきた」と感じることはないですか?
実は歯並びは経年的に変化し、お顔の印象も大きく変わることでしょう。
見た目だけではなく身体にも変化は現れ、老化が進む原因にもなります。
歯並びは老化と深く関係しているので、いつまでも健康な身体で若々しい見た目を保つためには「歯並び」が重要です。
歯並びと老化はどのような関係があるのか、詳しく説明していきます。
目次
歯並びと老化の関係性

加齢によって口腔内の状態は変化していきます。
徐々に変化するため、気付いた時には悪くなっていることが多いので、以下のことに気を付けて下さい。
1)歯並びが変化する
歯並びは頬と唇による外側からの圧力と、舌による内側からの圧力で保たれています。
しかし加齢とともに筋肉が弱くなることで歯をバランスよく保つことが難しくなります。
また、歯を支えている骨の骨密度が低下することが原因で歯が動きやすくなります。
前歯は前に傾いてくるので出っ歯やすきっ歯になり、上下顎の前歯の間が開き「開咬(オープンバイト)」になりやすいです。
親知らずが歯並びに影響を与えることがあります。
親知らずの本数や向きには個人差があり、0本の方もいれば4本の方もいて、真っすぐに生える方もいれば斜め、横向きに生える方もいます。
親知らずのスペースがあって真っすぐ生えれば比較的問題はないですが、スペースがない場合や斜めや横向きに埋まっている場合は、手前の歯を押すので歯並びが乱れてしまいます。
矯正後の後戻り防止や、将来歯並びが悪くなることを予防するために、予め親知らずを抜歯することも1つの方法です。
2)噛み合わせが悪くなる
加齢に伴い、歯並びの変化や歯茎や顎骨が収縮すること、歯が摩擦することで噛み合わせが悪くなることがあります。
歯が虫歯や歯周病で失った場合、放置していると両隣や対合の歯がそのスぺースを埋めるように動きます。
そうすると歯並びが乱れて噛み合わせが悪くなってしまいます。
また、奥歯の欠損や摩耗により前歯にかかる負担が増えるので、前歯が少しずつ動き、悪循環な環境になりやすいです。
噛み合わせが低くなってくると、口元のシワやほうれい線が目立つようになり、老けて見えることがあります。
また、噛み合わせが悪いことで表情筋が衰え、シワやほうれい線が目立つリスクが高くなります。
現在、歯並びが悪い方は噛み合わせも悪い可能性があるので、歯列矯正をすることで改善できます。
3)歯周病のリスクが高くなる
歯周病は年齢とともに進行しやすくなります。
加齢で免疫力が低下し、唾液の分泌量も減少するので細菌が増殖しやすい環境になります。
そして、歯茎が下がり歯根面が露出することで磨き残しが増えてしまうことや、歯周ポケットが深くなると炎症を引き起こし、歯周病が悪化します。
歯周病が進行すると歯の喪失リスクは高まり、食生活や歯並び・噛み合わせにも影響を及ぼします。
また、歯周病は全身の健康にも繋がるため、糖尿病や心疾患、脳卒中など全身疾患のリスクも高くなる傾向にあるので、歯周病の予防が重要です。
4)お口周りの筋肉が低下する
誰しもが経年的に全身の筋肉量や質が低下していきますが、お口周りの筋肉も例外ではありません。
お口周りの筋肉が低下することで、皮膚がたるみやすくなり、ほうれい線やシワが目立ちやすくなります。
また、食べ物を噛む力や舌を動かす力、飲み込む力なども低下するため誤嚥のリスクが高まります。
日本の高齢者の死因3位は、誤嚥した際に食べカスや口腔内の細菌が肺や気管支で炎症を起こす「誤嚥性肺炎」です。
これらを予防するためには、お口周りの筋肉を鍛える運動やバランスの摂れた食事、口腔内の環境を清潔に保つことが大切です。
歯並びの悪さを放置していると老化の進行が早く、老化により歯並びが悪くなることもあります。
歯並びと老化は相互関係にあるため、歯並びを整えて健康な口腔内環境を維持することが老化を防ぐことに繋がります。
歯並びと脳の関係性

歯並びは脳の老化にも深く関係しています。
歯並びが整っていて噛み合わせが正常な場合は、しっかり噛むことができます。
「噛む」ということは、噛む筋肉(咀嚼筋)が働くので神経を通じて脳に刺激が伝わります。
これにより脳の血流が増加するので脳の機能が活性化されるので、集中力や記憶力、判断力、反射神経などを向上させる効果があります。
そのため認知症の発症リスクを抑えることができるので、歯が健康だといつまでも自分の思考で楽しく人生を過ごせる可能性が高くなります。
残っている歯の本数が少ない人ほど認知症になりやすく、ご自身の歯の本数が多い人ほど脳が健康な高齢者が多いことがわかっています。
残存歯が少ないと「全体でしっかり噛めない」「食べ物を噛む回数が少なくなる」ということが脳への刺激が弱くなる原因になります。
その結果、刺激が伝達しなくなった脳神経は死滅していき、脳の働きが低下するので認知症の発症リスクが増加していくのです。
日本は人生100年時代に突入しているので、高齢者の割合が増加傾向にありますが、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
近年では65歳未満で発症する若年性認知症も増加傾向にあるので、不正咬合や若年性歯周病、噛む回数の減少が懸念されています。
噛むことは脳の機能を高めるほか、以下の効果も期待できます。
・噛む回数が多いと食べ物を細かく噛み砕くことができるので、消化しやすく胃腸の働きを助ける。
・脳の満腹中枢が刺激され、満腹感が得られやすくなるので肥満防止にも繋がる。
・唾液の分泌が促進されるので免疫力が高くなり、がんの予防にもなる。
・噛むと顔の筋肉が動くことで目の周りの血流が増加し、目の機能が向上して視力低下を防ぐ。
・口周りの筋肉が鍛えられるので唇や舌の動きがスムーズになり、はっきりと発音できるようになる。
など健康面でも様々なメリットが得られます。
脳の老化は予防すれば防げる可能性があるので、噛むことにも意識してみてください。
老化の予防

歯から身体を健康にし、老化の予防に効果があることを紹介します。
1)歯列矯正

歯並びを改善することで噛み合わせが左右対称になり、口周りの筋肉のバランスが整います。
また、歯並びが綺麗なことで自信が付き、普段から会話や笑うことが増えることで精神的にも健康になり、表情筋を鍛える事にも繋がります。
2)定期検診

定期的に歯科医院でクリーンニングを行うことで、磨き残しや歯石の蓄積を防ぎ、歯周病のリスクを下げることができます。
虫歯や歯周病の早期発見・早期治療ができるので、歯の寿命を長くすることができます。
3)栄養バランスの摂れた食事

歯や骨の健康をサポートするために、ビタミンやカルシウムなどバランスよく摂取することが大切です。
カルシウムには歯の質を強くする働きがあり、虫歯のリスクを減らす効果が期待できるので、乳製品や小魚・キャベツなどおすすめです。
また、歯を強化する「フッ素」が多く含まれているわかめや緑茶なども歯に良いです。
ビタミンは歯の形成に必要な栄養素なので、野菜や果物・レバー・海藻類を食べましょう。
リンゴは「自然の歯ブラシ」とも呼ばれており、唾液の分泌を促し口腔内の洗浄効果があります。
4)よく噛む

よく噛むことはアンチエイジング効果や脳の活性化、表情筋の強化など、様々な老化予防に繋がります。
食事の際に噛む回数を増やすこと、柔らかい食べ物ばかりでなく硬い物や歯ごたえのある物を食べるように心掛けましょう。
キシリトールや特定保健用食品のガムを噛むことも有効です。
5)禁煙

タバコに含まれるニコチンやタールなどの成分が歯周病の原因になるため、禁煙することで歯の老化予防には効果的です。
6)口元のトレーニング

口も周りの筋肉を鍛えるために、口元のトレーニングを行う習慣を付けると良いです。
トレーニングには次のようなものがあります。
・あいうべ体操
・パタカラ体操
・ベロ回し
・上向きうがい
・ペットボトル運動
まとめ

歯並びと老化について相互関係にあることがわかったと思います。
歯のケアを怠らず大切にすることも重要ですが、歯並びの状態も老化に関わってきます。
歯列矯正は何歳でも可能ですが、できるだけ早くに歯並びを改善することでより早く老化予防をすることができます。
歯並びや噛み合わせが気になる方はお気軽にお問い合わせください。






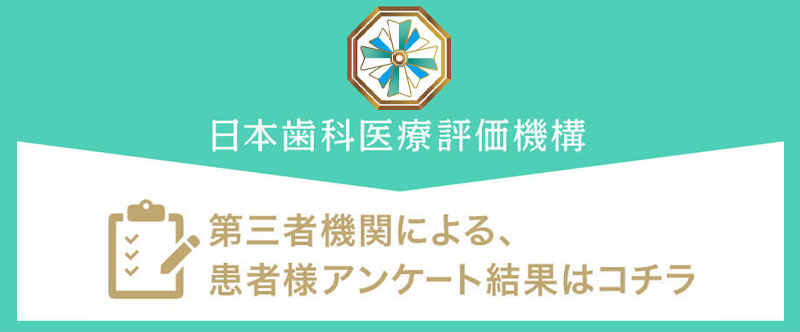
 治療ガイド
治療ガイド